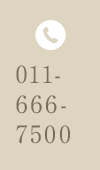「親知らずが歯並びに悪影響を与えるって本当?」「矯正治療をするなら親知らずは抜かないといけないの?」と不安に思っていませんか?この記事では、親知らずが歯並びに与える影響や、矯正治療との関係性について詳しく解説します。親知らずを抜くべきケース、抜かなくても良いケース、それぞれのメリット・デメリット、費用相場、抜歯後のケアまで網羅的にご紹介します。この記事を読めば、親知らずに関する疑問が解消され、ご自身にとって最適な選択ができるようになります。虫歯や歯周病のリスク、矯正治療の成功率にも関わる重要な情報なので、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. 親知らずとは?
親知らずとは、正式名称を第三大臼歯といい、永久歯の中で最も奥に生えてくる歯のことです。一般的に10代後半から20代前半に生えてきますが、中には30代以降に生えてくる場合や、全く生えてこない場合もあります。上下左右の顎に1本ずつ、計4本生えるのが一般的です。詳しくは、日本口腔外科学会のホームページをご覧ください。
親知らずという名前の由来は、生えてくる時期が遅いことから、親がその歯の存在を知らないうちに生えてくるため、または、昔は平均寿命が短く、親知らずが生える年齢まで生きることが珍しかったためなど、諸説あります。
1.1 親知らずの形状と生え方
親知らずは、他の奥歯と同様に食べ物をすり潰す役割がありますが、他の奥歯と比べて形状や生え方にいくつかの特徴があります。
- 大きさや形が一定ではない:他の奥歯と比べて、大きさや形にばらつきがあり、小さいものから大きいもの、通常の形のものから歪な形のものまで様々です。
- 斜めや横向きに生えることが多い:顎のスペースが不足している場合、斜めや横向きに生えてくることが多く、完全に生え切らずに歯茎に埋まったままの状態(埋伏歯)になることもあります。また、一部だけ歯茎から出ている状態(半埋伏歯)の場合もあります。
- 歯の根の本数が様々:親知らずの歯根の本数は、他の奥歯と比べて多く、2本から4本、場合によってはそれ以上の根を持つこともあります。また、歯根が曲がっている場合もあり、抜歯を難しくする要因となります。
1.2 親知らずが生えることによる問題
親知らずは、正常に生えていれば問題ありませんが、生え方や顎のスペースによっては様々な問題を引き起こす可能性があります。
| 問題 | 詳細 |
|---|---|
| 歯並びの悪化 | 親知らずが他の歯を押すことで、歯並びが乱れることがあります。 |
| 虫歯や歯周病のリスク増加 | 歯ブラシが届きにくく、磨き残しやすいため、虫歯や歯周病になりやすいです。 |
| 顎関節症 | 親知らずが顎の関節に負担をかけることで、顎関節症を引き起こす可能性があります。 |
| 嚢胞(のうほう)の形成 | 埋伏歯や半埋伏歯の場合、周囲の組織に嚢胞(液体の入った袋)ができることがあります。 |
| 智歯周囲炎 | 親知らずの周囲の歯茎が炎症を起こし、痛みや腫れが生じます。 |
これらの問題を予防するためにも、定期的な歯科検診で親知らずの状態をチェックすることが重要です。そして、必要に応じて抜歯などの適切な処置を受けるようにしましょう。
2. 親知らずが歯並びに与える影響
親知らずは、20歳前後で生えてくる奥歯です。現代人は顎が小さくなってきているため、親知らずが生えるスペースが不足し、様々な問題を引き起こす可能性があります。特に歯並びへの影響は大きく、放置することで将来的に矯正治療が必要になるケースもあります。親知らずが歯並びに与える影響について詳しく見ていきましょう。
2.1 親知らずが原因で起こる歯並びの悪化
親知らずが歯並びに悪影響を与える最も大きな原因は、スペースの不足です。顎に十分なスペースがない場合、親知らずは斜めや横向きに生えてきたり、完全に埋まったままになったりします。これが周りの歯を圧迫し、歯並び全体を乱す原因となります。
具体的には以下のような歯並びの悪化が起こりえます。
| 悪影響 | 詳細 |
|---|---|
| 歯の crowding(叢生) | 親知らずの圧迫により、他の歯が押し出され、歯並びがデコボコになる。 |
| 部分的な歯列不正 | 親知らずが生えている部分の歯並びだけが乱れる。 |
| 噛み合わせの悪化 | 歯並びの乱れにより、上下の歯の噛み合わせが悪くなる。 |
| 前歯の突出 | 親知らずが前歯を圧迫し、前歯が前に出てしまう。 |
2.2 歯並びが悪化することで起こる問題
歯並びが悪化すると、見た目の問題だけでなく、様々な機能面の問題も引き起こします。例えば、虫歯や歯周病のリスクが高まることが挙げられます。歯並びがデコボコしていると、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。また、噛み合わせが悪くなると、顎関節症を引き起こす可能性もあります。顎関節症は、顎の関節や周りの筋肉に痛みや違和感を感じる症状で、口が開けにくくなったり、顎を動かすと音がしたりするなどの症状が現れます。さらに、歯並びの悪化は、発音障害や咀嚼機能の低下にもつながる可能性があります。肩こりや頭痛の原因となるケースも報告されています。このように、歯並びの悪化は、様々な健康問題を引き起こす可能性があるため、早期の対処が重要です。
3. 親知らずの抜歯が必要なケース
親知らずの抜歯は、必ずしも全ての人に必要なわけではありませんが、様々な状況において推奨されます。特に、歯並びや口腔内の健康に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、抜歯が適切な選択肢となることが多いです。以下に、親知らずの抜歯が必要となる主なケースを詳しく解説します。
3.1 矯正治療における親知らず抜歯の必要性
矯正治療を行う際、親知らずの存在が治療計画の妨げになる場合があります。特に、歯列矯正でスペースを作る必要がある場合、親知らずを抜歯することで、他の歯を移動させるためのスペースを確保できます。親知らずを残したまま矯正治療を行うと、せっかくきれいに並んだ歯が後戻りしたり、治療期間が長引いたりする可能性があります。
また、親知らずが矯正後の歯並びを乱す原因となることもあります。矯正治療によって理想的な歯並びを実現した後でも、親知らずが生えてくることで、せっかく整えた歯並びが再び崩れてしまう可能性があるため、事前に抜歯しておくことが推奨されるケースが多いです。
3.2 親知らず抜歯のメリット
親知らずを抜歯することで得られるメリットは様々です。主なメリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 歯並びの改善 | 親知らずが原因で起こる歯列の乱れを予防・改善し、美しい歯並びを維持することができます。 |
| 虫歯・歯周病予防 | 親知らずは磨きにくいため虫歯や歯周病になりやすく、周囲の歯にも悪影響を及ぼす可能性があります。抜歯することでこれらのリスクを軽減できます。 |
| 顎関節症の予防・改善 | 親知らずが顎関節に負担をかけている場合、顎関節症の症状を悪化させる可能性があります。抜歯によって顎関節への負担を軽減し、症状の改善が期待できます。 |
| 口内炎の予防 | 親知らずが頬粘膜を刺激することで、口内炎を繰り返す場合があります。抜歯することで口内炎の発生リスクを低減できます。 |
| 矯正治療の効率化 | 矯正治療前に親知らずを抜歯することで、治療期間の短縮や治療効果の向上に繋がることがあります。 |
| 口腔内の清潔維持 | 親知らずは歯ブラシが届きにくく、歯垢や食べカスが溜まりやすい場所です。抜歯することで口腔内全体の衛生状態を改善しやすくなります。 |
これらのメリットを考慮し、歯科医師とよく相談した上で抜歯の必要性を判断することが重要です。自己判断で抜歯をせずに、必ず専門家の意見を仰ぎましょう。
4. 親知らずの抜歯が不要なケース
親知らずの抜歯は必ずしも必要ではありません。状況によっては、抜歯のリスクや費用に見合うメリットがない場合もあります。抜歯が不要なケースを以下にまとめました。
4.1 親知らずが完全に骨の中に埋まっているケース
親知らずが完全に骨の中に埋まっており、痛みや腫れなどの症状がなく、周囲の組織への影響がない場合は、抜歯の必要性は低いと考えられます。ただし、定期的なレントゲン検査で経過観察を行い、将来的に問題が発生する可能性がないか確認することが重要です。
4.2 親知らずが正常に生えており、噛み合わせに問題がないケース
親知らずがまっすぐ生えており、上下の歯と正常に噛み合っており、歯磨きなどのケアも問題なく行える場合は、抜歯の必要はありません。このようなケースでは、親知らずも他の歯と同じように大切な歯として機能しているため、無理に抜歯する必要はありません。
4.3 親知らずが虫歯や歯周病になっていないケース
親知らずが虫歯や歯周病になっておらず、口腔内の衛生状態が良好に保たれている場合は、抜歯の必要性は低いです。しかし、親知らずは磨きにくいため、将来的に虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性も考慮する必要があります。 定期的な歯科検診を受け、適切なケアを行うことが重要です。
4.4 全身状態に問題があるケース
重度の心臓病や糖尿病、血液疾患などの持病がある場合、抜歯に伴うリスクが高まる可能性があります。このような場合は、担当医とよく相談し、抜歯の必要性とリスクを慎重に検討する必要があります。 妊娠中の方なども、安定期に入るまでは抜歯を避けることが推奨されます。
4.5 高齢者のケース
高齢者の場合、抜歯に伴う身体への負担が大きくなる可能性があります。そのため、症状がない場合は、経過観察を選択することがあります。 しかし、親知らずが原因で炎症や感染症などを引き起こしている場合は、抜歯が必要となる場合もあります。
4.6 親知らず抜歯のリスク・デメリット
親知らずの抜歯には、以下のようなリスクやデメリットも存在します。抜歯が必要かどうか判断する際には、これらのリスクも考慮に入れる必要があります。
| リスク・デメリット | 内容 |
|---|---|
| ドライソケット | 抜歯後に血餅が剥がれ落ちてしまうことで、骨が露出してしまう状態。強い痛みや炎症を引き起こす可能性があります。 |
| 神経損傷 | 親知らずの近くには下歯槽神経や舌神経が通っているため、抜歯時にこれらの神経が損傷されるリスクがあります。知覚麻痺やしびれなどの後遺症が残る可能性があります。 |
| 感染症 | 抜歯窩に細菌が感染し、炎症を起こす可能性があります。 |
| 出血 | 抜歯後に止血が困難な場合や、持病などによって出血が長引く場合があります。 |
| 腫れや痛み | 抜歯後には、腫れや痛みを伴うのが一般的です。通常は数日で治まりますが、強い痛みや腫れが長引く場合は、歯科医院を受診する必要があります。 |
| 開口障害 | 抜歯後に顎の筋肉が炎症を起こし、口が開きにくくなることがあります。 |
4.7 抜歯後の痛みや腫れ
親知らずの抜歯後には、痛みや腫れが生じることが一般的です。痛みや腫れの程度は、親知らずの状態や抜歯の難易度によって異なります。 通常、痛みや腫れは数日で治まりますが、強い痛みや腫れが長引く場合は、歯科医院を受診してください。痛みを抑えるために、鎮痛剤が処方されることもあります。また、腫れを軽減するために、患部を冷やすことも効果的です。抜歯後の注意事項をよく守り、適切なケアを行うことで、痛みや腫れを最小限に抑えることができます。
5. 親知らず抜歯と矯正治療の費用相場
親知らずの抜歯と矯正治療は、それぞれ費用が異なります。また、抜歯や矯正治療の方法によっても費用は変動します。費用の目安を把握し、治療計画を立てる際の参考にしてください。
5.1 親知らず抜歯の費用相場
親知らずの抜歯費用は、抜歯の難易度によって大きく異なります。水平埋伏智歯や歯根が曲がっているなど、抜歯が難しい場合は費用が高額になる傾向があります。また、大学病院などの大きな病院の方が、費用が高くなる傾向があります。抜歯の方法も、通常の抜歯と外科的抜歯で費用が異なります。
| 抜歯の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 通常の抜歯 | 3,000円~5,000円程度 |
| 水平埋伏智歯の抜歯 | 8,000円~15,000円程度 |
| 歯根が曲がっている親知らずの抜歯 | 5,000円~10,000円程度 |
| 外科的抜歯 | 10,000円~20,000円程度 |
上記はあくまでも目安であり、医療機関によって費用は異なるため、事前に確認することが重要です。また、CT撮影が必要な場合は、別途5,000円~10,000円程度の費用がかかる場合があります。
5.2 矯正治療の費用相場
矯正治療の費用は、使用する装置の種類や治療期間、治療内容によって大きく異なります。子供と大人でも費用が異なる場合があります。また、医療機関によっても費用設定が異なるため、複数の医療機関で見積もりを取ることをおすすめします。
| 矯正装置の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| メタルブラケット(ワイヤー矯正) | 50万円~80万円程度 |
| セラミックブラケット | 70万円~100万円程度 |
| マウスピース矯正(インビザラインなど) | 70万円~120万円程度 |
| 部分矯正 | 20万円~50万円程度 |
| 子供の矯正治療(床矯正) | 20万円~50万円程度 |
矯正治療には、検査費用、診断費用、調整費用、保定装置費用などが含まれる場合があります。総額費用を事前に確認し、支払い方法についても相談しておくことが大切です。
医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の料金料は以下をご覧ください。
5.2.1 医療費控除について
親知らずの抜歯や矯正治療は、医療費控除の対象となる場合があります。確定申告を行うことで、一定額の所得控除を受けることができます。医療費控除を受けるためには、医療機関から発行される領収書が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。医療費控除の適用範囲や手続き方法については、国税庁のウェブサイトなどを参照してください。
6. 親知らず抜歯に関するよくある質問
ここでは、親知らずの抜歯に関するよくある質問にお答えします。
6.1 矯正前に親知らずの抜歯は必要?
必ずしも矯正前に親知らずの抜歯が必要なわけではありません。親知らずの状態や矯正治療の計画によって異なります。親知らずが既に生えていて、歯並びに悪影響を与えている場合や、矯正治療のスペース確保のために抜歯が必要となる場合は、矯正前に抜歯を行うことが多いです。しかし、親知らずが埋伏していて問題がない場合や、矯正治療に影響がない場合は、抜歯を行わないこともあります。矯正歯科医が個々の状況を判断し、適切なタイミングで抜歯を行うかどうかを決定します。
6.2 親知らずの抜歯は痛い?
抜歯中は麻酔が効いているため痛みを感じることはありません。麻酔が切れた後は、痛みや腫れ、出血などが起こる可能性があります。痛みや腫れの程度は個人差がありますが、処方された痛み止めを服用することでコントロールできます。また、抜歯後の注意事項をよく守り、安静にすることで、痛みや腫れを軽減することができます。心配な場合は、遠慮なく歯科医師に相談しましょう。
6.3 抜歯後の食事はどうすればいい?
抜歯後は、血餅と呼ばれる血液の塊が傷口を保護するために重要です。血餅が剥がれてしまうと、ドライソケットと呼ばれる症状を引き起こし、強い痛みを伴うことがあります。そのため、抜歯後しばらくは、食事の内容に注意が必要です。
6.3.1 抜歯後、食べてはいけないもの
- 刺激物(辛いもの、熱いもの、酸っぱいものなど)
- アルコール
- 硬いもの(せんべい、ナッツ、フランスパンなど)
- 粘着性のあるもの(キャラメル、ガムなど)
6.3.2 抜歯後、食べて良いもの
- ヨーグルト
- プリン
- おかゆ
- うどん
- 煮物(柔らかく煮込んだもの)
抜歯後数日間は、上記のような食事を心がけ、抜歯した側で噛まないように注意しましょう。また、ストローの使用は控えるようにしてください。口の中の圧力の変化により、血餅が剥がれてしまう可能性があります。
6.4 抜歯にかかる時間は?
親知らずの抜歯にかかる時間は、親知らずの状態や、埋伏の有無によって大きく異なります。まっすぐ生えていて簡単に抜ける場合は、数分から10分程度で終わることもありますが、横向きに埋伏している場合や、骨の中に深く埋まっている場合は、1時間以上かかることもあります。事前に歯科医師に抜歯にかかる時間の見通しを聞いておくと安心です。
6.5 妊娠中は抜歯できる?
妊娠中は、安定期(妊娠5ヶ月~7ヶ月)であれば、緊急性の高い抜歯は可能です。ただし、妊娠初期や後期は、母体や胎児への影響を考慮し、抜歯を避けることが推奨されます。どうしても抜歯が必要な場合は、産婦人科医と相談の上、慎重に判断する必要があります。また、授乳中も薬の影響を考慮する必要がありますので、歯科医師に相談しましょう。
6.6 親知らずの抜歯後の腫れはいつまで続く?
親知らずの抜歯後の腫れのピークは、抜歯後2~3日後と言われています。その後、徐々に腫れは引いていきますが、1週間程度は腫れが残ることもあります。腫れが長引く場合や、強い痛みを伴う場合は、ドライソケットや感染症の可能性も考えられますので、速やかに歯科医師に相談しましょう。
6.7 親知らずを抜くと小顔になるってホント?
親知らずを抜歯することで、直接的に小顔になることはありません。親知らずの抜歯によって、顎の骨の体積がわずかに減少することはありますが、その変化は見た目にはほとんどわからない程度です。親知らずの抜歯と小顔効果の関係性については、科学的な根拠はありません。
6.8 セカンドオピニオンは必要?
セカンドオピニオンを受けることは、患者さんの権利です。特に、抜歯が必要かどうか迷っている場合や、治療方針に不安がある場合は、他の歯科医師の意見を聞くことで、より納得のいく治療を受けることができます。セカンドオピニオンを受けることで、様々な治療法の選択肢を知ることができ、自分に最適な治療法を選択することができます。
7. まとめ
親知らずの抜歯は、矯正治療の成功や歯並びの維持に大きく関わることがあります。親知らずが歯並びに悪影響を与える場合、例えば歯列が乱れたり、虫歯や歯周病のリスクが高まる場合は、抜歯が推奨されます。矯正治療においては、歯を動かすスペースを確保するために抜歯が必要となるケースもあります。一方で、親知らずがまっすぐ生えていて、他の歯に悪影響を与えていない場合は、必ずしも抜歯は必要ありません。抜歯には痛みや腫れなどのリスクも伴いますので、歯科医師とよく相談し、ご自身の状況に合った判断をすることが重要です。費用面も考慮し、納得した上で治療を進めましょう。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。